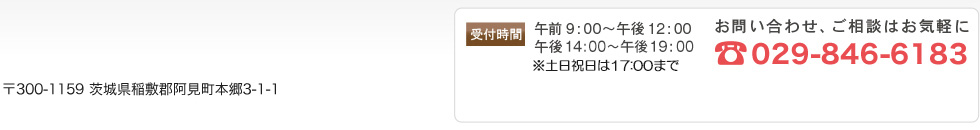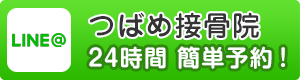Blog記事一覧 > EMS | つばめ接骨院|阿見町の記事一覧
坐骨神経痛でお悩みの方へ|その痛み、我慢していませんか?
「お尻から太もも、ふくらはぎにかけてズーンと痛む」「長時間座っているとつらい」「立ち上がる瞬間にビリッと痛む」
このような症状がある方は、坐骨神経痛の可能性があります。
坐骨神経痛とは、腰から足先まで伸びる坐骨神経が圧迫・刺激されることで起こる症状の総称です。原因は一つではなく、骨盤や背骨の歪み、筋肉の緊張、姿勢の崩れ、長時間のデスクワークや運動不足など、日常生活の積み重ねが影響していることが多くあります。
特に多いのが、骨盤の歪みや腰回り・お尻の筋肉が硬くなることで神経を圧迫してしまうケースです。そのため、痛みが出ている部分だけを揉んでも、一時的に楽になるだけで根本的な改善につながらないことも少なくありません。
当院では、痛みの出ている場所だけでなく、骨盤や背骨のバランス、筋肉の状態、身体全体の使い方を丁寧に確認しながら施術を行います。無理に強い刺激を加えるのではなく、身体に負担の少ない施術で神経へのストレスを軽減し、再発しにくい状態を目指します。
「病院では異常なしと言われた」「薬や湿布だけでは変わらない」「できれば手術は避けたい」
そんな方こそ、一度ご相談ください。坐骨神経痛は、早めにケアを始めることで改善までの期間が短くなるケースも多い症状です。
つらい痛みを我慢せず、日常生活を快適に過ごせる身体づくりを一緒に目指していきましょう。
◾️ご予約・お問い合わせはこちら
📍ホームページ
▶ https://smr-group.jp/
📷Instagram
▶ https://www.instagram.com/tsubame0520/
💬LINEでかんたん予約・相談
▶ https://page.line.me/ylz0052s
繰り返す腰痛、そのままにしていませんか?
腰痛は日本人の多くが一度は経験すると言われている、とても身近な不調です。
「朝起きたときに腰が重い」「長時間座っていると痛くなる」「ぎっくり腰を何度も繰り返している」など、症状は人それぞれですが、日常生活に大きな影響を与えてしまいます。
腰痛の原因は、腰そのものだけにあるとは限りません。
姿勢の乱れ、骨盤の歪み、筋肉の硬さ、筋力低下、日常生活のクセなど、さまざまな要因が重なって起こることがほとんどです。
腰痛の原因になりやすい生活習慣
現代人は、知らず知らずのうちに腰へ負担をかける生活をしています。
-
デスクワークやスマホ操作による前かがみ姿勢
-
長時間同じ姿勢で過ごす
-
運動不足による筋力低下
-
足を組む、片側に体重をかけるクセ
これらが積み重なることで、骨盤や背骨のバランスが崩れ、腰に過剰な負担がかかってしまいます。
腰痛を放置するとどうなる?
「我慢すればそのうち良くなる」と放置してしまうと、
痛みが慢性化したり、動くのが怖くなってさらに身体を動かさなくなったりする悪循環に陥ることがあります。
また、腰だけでなく、お尻や脚にしびれが出てくるケースも少なくありません。
だからこそ、早めのケアと原因へのアプローチが大切です。
腰痛改善に大切なポイント
腰痛改善のためには、痛い部分だけを見るのではなく、身体全体のバランスを確認することが重要です。
-
骨盤や背骨の歪みチェック
-
筋肉の緊張を和らげるケア
-
正しい姿勢の意識づけ
-
再発を防ぐためのセルフケア指導
一人ひとりの身体の状態に合わせたケアを行うことで、腰への負担を減らし、痛みの出にくい身体づくりを目指します。
こんな方はぜひご相談ください
-
慢性的な腰痛に悩んでいる
-
何度も腰痛を繰り返している
-
病院では異常がないと言われた
-
根本から身体を整えたい
腰痛は、正しいケアを行うことで改善が期待できます。
つらい症状を我慢せず、まずはお気軽にご相談ください。
◾️ご予約・お問い合わせはこちら
📍ホームページ
▶ https://smr-group.jp/
📷Instagram
▶ https://www.instagram.com/tsubame0520/
💬LINEでかんたん予約・相談
▶ https://page.line.me/ylz0052s
ある日突然、腰に「ギクッ」と激しい痛みが走り、立てなくなる――それが「ぎっくり腰」。医学的には「急性腰痛症」と呼ばれることもあり、腰まわりの筋肉・靭帯・関節などに急な負荷がかかることで発症します。中腰で重い物を持ち上げたとき、急な体の動き、さらにはちょっとしたくしゃみや前かがみから……。思いがけないタイミングで襲ってくることも多く、「まさか自分が」という油断が危険です。
ぎっくり腰は、単なる“腰の痛み”ではありません。場合によっては日常生活がままならなくなるほど重症化することもあるので、「時間が経てば自然に治るだろう」と軽く考えるのはおすすめできません。
なぜ起きるのか? — 原因ときっかけ
ぎっくり腰の主な原因は、腰まわりの筋肉・筋膜や靭帯、関節に対する急激な負荷や捻じれ、あるいは“無理な姿勢”の継続など。腰を支える筋力が弱かったり、姿勢が崩れていたりすると、ちょっとした動きがトリガーになりやすくなります。
また、日頃から同じ姿勢で長時間座り続けたり、運動不足や筋肉の硬さがあったり、体の柔軟性が低いと、ぎっくり腰のリスクは高まります。普段から腰に負担をかける習慣がある人は、要注意です。
どう対処すればいいか? — 初期対応のポイント
もしぎっくり腰になってしまったら、まず大切なのは「無理しないこと」。激しい痛みがあるうちは、必要以上に動かさず、安静を心がけましょう。痛みが落ち着いたら、温めるなどを行い腰を軽く支えるコルセット・サポーターの使用などで、炎症や負担を和らげるのがおすすめです。ただし、長期間ずっと固定し続けるのは逆効果。筋力低下や体のバランス悪化につながる可能性があります。
そして、痛みがある程度治まったら、無理のない範囲で軽いストレッチや姿勢改善を始め、腰まわりの筋肉や関節の柔軟性を取り戻すことが大切です。
つばめ接骨院の“根本改善”アプローチ
つばめ接骨院では、ぎっくり腰などの腰痛に対し、「ただ痛みを取り除くだけで終わらない」ことを大切にしています。初診時には丁寧な問診・検査を行い、骨格・筋肉・姿勢・生活習慣などを総合的にチェック。そこから、あなたに合った“オーダーメイドの施術プラン”を提案します。
矯正は「ボキボキしない、ソフトな施術」を基本としていて、高齢の方、お子さま、産後の方なども安心して受けられます。 また、施術後には“自宅でできるセルフケア”の指導もあり、施術と生活習慣の両面から、再発しにくい身体づくりを目指します。
ぎっくり腰を繰り返さないためには、日頃の姿勢や動作、生活習慣の見直しが欠かせません。
- 重い物を持つときは膝を曲げて腰に負担をかけない
- 長時間同じ姿勢を続けず、適度に体を動かす
- 腰まわりの筋肉、体幹(インナーマッスル)を鍛えるストレッチや運動
- 冷えや血行不良を避ける生活習慣
そして、体に違和感を感じたら、早めにつばめ接骨院で治療受けるのオススメします。つばめ接骨院のような“根本改善を目指す院”で、身体の土台を整えることは、ぎっくり腰を「たまたまの痛み」で終わらせず、「再発しない体づくり」への第一歩になります。
◾️ご予約・お問い合わせはこちら
📍ホームページ
▶ https://smr-group.jp/
📷Instagram
▶ https://www.instagram.com/tsubame0520/
💬LINEでかんたん予約・相談
▶ https://page.line.me/ylz0052s
【寝違えはなぜ起こる?原因と早期改善のポイント|つばめ接骨院】
朝起きた瞬間、「あれ?首が回らない…」という経験はありませんか?
寝違えは多くの方が一度は経験する症状ですが、原因を理解し、適切に対処することで早期改善が可能です。ここでは、寝違えの原因や注意点、つばめ接骨院でのアプローチについて分かりやすくまとめました。
■ 寝違えが起こる原因とは?
寝違えは、睡眠中の姿勢や筋肉の状態が原因で起こる首周りの急性症状です。
1. 無理な寝姿勢
・枕が合わず首が不自然に曲がったまま寝ている
・ソファやうつ伏せ寝で長時間同じ姿勢をキープしている
睡眠中は意識がないため、関節や筋肉に負担がかかっても自分では気づけません。その結果、強い張りや炎症につながることがあります。
2. 筋肉の疲労・緊張
日頃のスマホ・デスクワークで首の筋肉が硬くなっていると、少しの負担でも炎症が起きやすくなります。
「寝ているだけなのに痛めた」というのは、実は“その前から筋肉が限界”というサインでもあります。
3. 寒さによる血流低下
季節の変わり目や冷房で首が冷えると、筋肉の柔軟性が低下します。硬くなった状態で寝ると寝違えリスクが上昇します。
■ 痛くなった時にやってはいけないこと
痛いからといって自己流ケアをすると、かえって悪化することもあります。
× 無理にストレッチして伸ばす
× 痛い部分を強く揉みほぐす
× 首をバキっとひねる
× 湿布だけで何日も放置
寝違え直後は炎症があることが多いため、過度な刺激は逆効果です。
■ 自分でできる初期ケア
● アイシング(10分程度)
痛みが強い場合は炎症を抑える効果があります。
● 湿布よりも「安静」
炎症が落ち着くまでは首を動かしすぎないようにしましょう。
● 姿勢の見直し
デスクワーク中の姿勢を整えるだけで回復のスピードが変わります。
■ 当院での寝違え施術について
つばめ接骨院では、寝違えを「なぜ起きたのか」を徹底的に分析し、その原因まで改善する施術を行っています。
● 首の筋肉だけでなく、肩・背中・骨盤の状態もチェック
● 特殊電気療法で炎症を早期に抑える
● 筋緊張を緩め、可動域を改善
● 再発しにくい姿勢・動作の指導
「たかが寝違え」と思って放置すると、慢性的な首こりや頭痛につながるケースも多くあります。
痛みが強い場合や、2~3日経っても変化がない場合は早めの来院をおすすめします。
■ 寝違えは“生活習慣のサイン”
寝違えは病名ではなく、首の筋肉や関節がSOSを出している状態です。
一度痛めると日常生活に大きな支障が出るため、早めに正しくケアをして原因から改善していきましょう。
◾️ご予約・お問い合わせはこちら
📍ホームページ
▶ https://smr-group.jp/
📷Instagram
▶ https://www.instagram.com/tsubame0520/
💬LINEでかんたん予約・相談
▶ https://page.line.me/ylz0052s
【変形性膝関節症にお悩みの方へ】つばめ接骨院が解決します!
「歩くと膝がズキッと痛む」「階段の上り下りがつらい」「正座ができない」
そんなお悩みはありませんか?
それ、変形性膝関節症かもしれません。
◾️変形性膝関節症とは?
変形性膝関節症は、膝の軟骨がすり減り、骨と骨がぶつかることで炎症や痛みが起こる症状です。中高年の方に多く見られ、放置すると膝の変形が進み、日常生活に大きな支障をきたします。
原因としては、加齢による軟骨の摩耗だけでなく、肥満・筋力低下・O脚なども関係します。若い頃のスポーツでのケガや膝の酷使がきっかけとなることもあります。
◾️こんな症状ありませんか?
✅ 階段の上り下りで膝が痛む
✅ 歩くと膝がズキッとする
✅ 正座やしゃがみ動作ができない
✅ 膝が腫れて重だるい
✅ 膝の動きが硬くなり不安定に感じる
このような症状がある場合、変形性膝関節症の可能性があります。放置すると症状が悪化し、人工関節手術が必要になるケースもあります。早めの対処が大切です。
◾️変形性膝関節症の進行段階
初期:歩行時や立ち上がり時に痛みを感じる
中期:階段の昇降がつらくなり、膝が腫れたり変形が進む
末期:安静時にも痛みがあり、関節の可動域が大きく制限される
段階に応じた適切なケアが必要です。
◾️つばめ接骨院でできること
当院では、変形性膝関節症の患者様一人ひとりに合わせた施術を行っています。
✔ 膝周囲の筋肉を調整し、関節の負担を軽減
✔ 血流を改善し炎症を和らげる手技・電気療法
✔ EMSを用いた太ももの筋肉強化で膝の安定性を向上
✔ 姿勢や歩き方、日常生活での膝の使い方指導
✔ 自宅でできるストレッチ・セルフケアのアドバイス
膝の痛みを根本から改善し、再発予防までサポートします。
◾️お気軽にご相談ください!
「これって年齢のせいかな…」と諦める前に、ぜひ一度ご相談ください。
痛みの原因をしっかり見極め、あなたに合った施術プランをご提案します。
◾️ご予約・お問い合わせはこちら
📍ホームページ
▶ https://smr-group.jp/
📷Instagram
▶ https://www.instagram.com/tsubame0520/
💬LINEでかんたん予約・相談
▶ https://page.line.me/ylz0052s
◾️最後に
変形性膝関節症は放置すると進行してしまいますが、適切なケアで症状を軽減し、快適な生活を取り戻すことが可能です。
「少し膝が痛い」その小さなサインを見逃さず、早めにご相談ください。
私たちがあなたの膝の健康を全力でサポートします。
【四十肩にお悩みの方へ】つばめ接骨院が解決します!
「腕が上がらない」「肩がズキッと痛む」「洋服の着脱がつらい」
そんなお悩みはありませんか?
それ、**四十肩(五十肩)**かもしれません。
◾️四十肩とは?
四十肩とは、肩関節のまわりに炎症が起き、動かすと痛みが出たり、腕が上がらなくなる症状の総称です。正式には「肩関節周囲炎」と呼ばれ、40代以降の方に多く見られる症状です。
発症の原因はさまざまですが、多くは加齢による組織の変化・血行不良・姿勢不良などが複合的に関係しているといわれています。
◾️こんな症状ありませんか?
✅ 腕を上げると肩がズキッと痛む
✅ 夜中に肩の痛みで目が覚める
✅ シャツを着る・ブラを外す動作がつらい
✅ 肩が動かしづらく、日常生活に支障がある
こういった症状がある方は、四十肩の初期症状かもしれません。
放置すると肩の可動域がどんどん狭くなり、回復に1年以上かかることも。早めの対処が肝心です。
◾️四十肩の回復ステップ
四十肩は大きく3つの段階を経て回復します。
-
急性期:ズキズキした痛みが強く、安静が必要
-
拘縮期:痛みは落ち着くが、肩の動きが制限される
-
回復期:少しずつ可動域が戻る
それぞれの段階に応じた正しいケアが大切です。
◾️つばめ接骨院でできること
当院では、四十肩でお悩みの方に向けてその方の状態に合わせたオーダーメイド施術を行っています。
✔ 肩関節の可動域を広げる手技療法
✔ 血流促進による炎症軽減の電気療法・温熱療法
✔ 痛みの根本にアプローチする姿勢・体の使い方の指導
✔ 自宅でできるストレッチやセルフケアのアドバイス
特に、急性期の痛みを無理に動かすのは逆効果。プロの判断と施術で安全に改善へ導きます。
◾️お気軽にご相談ください!
「これって四十肩かな?」と気になったら、ぜひ一度ご相談ください。
どんな些細な症状でもしっかりお話を伺い、あなたに合った施術をご提案します。
◾️ご予約・お問い合わせはこちら
📍ホームページ
▶ https://smr-group.jp/
📷Instagram
▶ https://www.instagram.com/tsubame0520/
💬LINEでかんたん予約・相談
▶ https://page.line.me/ylz0052s
◾️最後に
四十肩は放っておくと日常生活に支障が出るだけでなく、治るまでに長い時間がかかってしまうこともあります。
「なんとなく肩が痛い」その小さな違和感こそ、体からのサインです。
私たちが一人ひとりに寄り添い、早期回復をサポートします。
#ハッシュタグ活用もどうぞ!
#四十肩 #五十肩 #肩の痛み #肩こり #整体 #マッサージ #肩関節周囲炎 #守谷市 #取手市 #つばめ接骨院 #接骨院 #リラクゼーション #肩の可動域改善 #肩が上がらない
脊柱管狭窄症でお悩みの方へ~つばめ接骨院の対応とは~
「最近、歩いていると足がしびれる」「少し休むと楽になるけど、また歩くと痛くなる」…このようなお悩みがある方は、脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)のかもしれません。
脊柱管狭窄症は、背骨の中にある「脊柱管」という神経の通り道が加齢や姿勢の崩れ、骨の変形などで狭くなり、神経を圧迫することで腰やお尻、脚に痛みやしびれを引き起こす症状です。特に50代以降の方に多く見られ、「間欠性跛行(かんけつせいはこう)」と呼ばれる、歩くとつらくなり休むと楽になる特徴があります。
当院の考える根本原因とは?
つばめ接骨院では、症状の「表面的な痛み」だけでなく、その背景にある姿勢のゆがみや筋力の低下、骨格バランスの崩れに注目します。
脊柱管狭窄症の方の多くに共通して見られるのは、
- 骨盤の前傾・後傾
- 背骨の過度なカーブ
- インナーマッスルの弱化
- 長年の悪い姿勢の積み重ね
これらが神経の通り道を圧迫し、症状を悪化させているのです。
つばめ接骨院での施術方法
当院では、脊柱管狭窄症に対して以下のようなアプローチを行っています。
・マッサージ、電気治療
・骨格矯正
背骨や骨盤の歪みを整えることで、神経が圧迫されにくい正しい姿勢へと改善していきます。無痛矯正を行い、少しずつ身体のバランスを整えます。
・筋肉調整
長年の緊張で硬くなってしまった腰やお尻、太もも周辺の筋肉を丁寧に緩め、血流や神経の通りを良くしていきます。
・EMSによるインナーマッスル強化
寝たままインナーマッスルを鍛えられる「EMS」を導入し、姿勢を支えるインナーマッスルを効率よく鍛えます。運動が難しい方、時間が作れない方などにおすすめです。
・日常動作や姿勢のアドバイス
生活習慣や歩き方、座り方のクセまで丁寧にカウンセリング。再発しにくい身体づくりをサポートします。
手術を避けたい方こそご相談ください!
脊柱管狭窄症と診断され、「もう手術しかない」と言われた方でも、当院のように身体の根本から整える施術によって、症状が軽減・改善するケースが多数あります。
もちろんすべての方に手術が不要というわけではありませんが、「できるだけ切らずに治したい」「日常生活を楽にしたい」というお気持ちに寄り添った施術を行っています。
脊柱管狭窄症は年齢とともに誰にでも起こりうる症状ですが、適切なケアと正しい姿勢づくりで、日常生活の負担を大きく軽減できます。
「最近歩くと脚がつらい」「病院では異常なしと言われたけど、良くならない」…そんなお悩みがある方は、一度つばめ接骨院にご相談ください!
ホームページ
(つばめ接骨院・すずらん接骨院)https://smr-group.jp/
インスタグラム
つばめ接骨院→https://www.instagram.com/tsubame0520/
すずらん接骨院→https://www.instagram.com/suzuransekkotu0321/
ライン
つばめ接骨院→https://page.line.me/ylz0052s
すずらん接骨院→https://page.line.me/beq9734a
腰痛の原因と対策
腰痛は現代人にとって非常に身近な問題の一つです。デスクワークが増え、長時間同じ姿勢を続けることが多くなった結果、多くの人が腰痛に悩まされています。この記事では、腰痛の主な原因とその対策について詳しく解説していきます。
腰痛の主な原因
腰痛にはさまざまな原因がありますが、特に以下のようなものが一般的です。
-
姿勢の悪さ 長時間のデスクワークやスマートフォンの使用によって、前かがみの姿勢が続くと腰に負担がかかりやすくなります。猫背や反り腰の姿勢は、腰への負担を増加させる原因となります。
-
筋力の低下 腰を支えるための筋肉(特に腹筋や背筋)が弱いと、腰に余計な負担がかかります。運動不足が原因で筋力が低下すると、腰痛が発生しやすくなります。
-
ストレスや疲労 精神的なストレスが腰痛を引き起こすこともあります。ストレスを感じると筋肉が緊張し、それが慢性的な腰痛へとつながることがあります。
-
椎間板ヘルニアや坐骨神経痛 椎間板の変形や神経の圧迫が原因で腰痛が発生することもあります。この場合、しびれや強い痛みを伴うことが多く、適切な治療が必要です。
腰痛対策
腰痛を予防・改善するためには、以下のような対策が有効です。
-
正しい姿勢を意識する デスクワークの際は、椅子に深く座り、背もたれを活用することで正しい姿勢を保ちましょう。また、スマートフォンの使用時も、画面を目の高さに持ってくることで、前かがみの姿勢を防ぐことができます。
-
適度な運動を取り入れる ウォーキングやストレッチ、筋トレを習慣化することで、腰を支える筋肉を強化できます。特に、体幹を鍛えるトレーニング(プランクやスクワットなど)は腰痛予防に効果的です。
-
ストレスを管理する ヨガや瞑想、深呼吸などのリラックス方法を取り入れ、ストレスを軽減しましょう。ストレスが原因で筋肉が緊張し、腰痛を引き起こすことがあるため、心のケアも重要です。
-
適切な寝具を選ぶ 硬すぎず柔らかすぎないマットレスや枕を選ぶことで、寝ている間の腰への負担を軽減できます。自分に合った寝具を選び、質の良い睡眠を心がけましょう。
-
整体やマッサージを利用する 腰の痛みが続く場合は、整体やマッサージで体の歪みを整えるのも有効です。ただし、慢性的な痛みがある場合は、医師の診察を受けることをおすすめします。
まとめ
腰痛は日常生活の中で意識することで予防・改善が可能です。正しい姿勢を保つこと、適度な運動をすること、ストレスを管理することなどを心がけ、健康的な生活を送りましょう。もし腰痛が長引く場合は、専門家に相談し、適切な治療を受けることが重要です。
ホームページ
(つばめ接骨院・すずらん接骨院)https://smr-group.jp/
インスタグラム
つばめ接骨院→https://www.instagram.com/tsubame0520/
すずらん接骨院→https://www.instagram.com/suzuransekkotu0321/
ライン
つばめ接骨院→https://page.line.me/ylz0052s
すずらん接骨院→https://page.line.me/beq9734a
こんにちは!
つばめ接骨院です!
坐骨神経痛は、腰から足先まで伸びる坐骨神経が圧迫・刺激されることで生じる症状です!
主な原因として、腰椎椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症などが挙げられますが、実際には腰の筋肉の緊張が大きく関与しています。
筋肉の硬直により坐骨神経が刺激され、痛みやしびれが引き起こされます。
症状は、腰からお尻、太もも、ふくらはぎ、足先にかけての痛みやしびれ、重だるさなど多岐にわたります。放置すると、感覚麻痺が進行し、歩行が困難になることもあります。
また、痛みをかばうことで骨盤や骨格の歪みが生じ、全身のバランスが乱れ、肩や背中など別の部位に新たな症状が現れる可能性もあります。
当院では、坐骨神経痛の根本原因である筋肉の緊張を解消するため、マッサージや電気治療を用いて筋肉をほぐし、血流を改善します。さらに、骨盤・骨格の歪みを矯正し、全身のバランスを整えることで、再発防止を図ります。 一人ひとりの体の状態に合わせたオーダーメイドの施術を提供し、症状の改善を目指します。
坐骨神経痛は、適切な施術とケアによって改善が期待できます。痛みやしびれでお悩みの方は、ぜひ一度当院にご相談ください。
ホームページ
(つばめ接骨院・すずらん接骨院)https://smr-group.jp/
インスタグラム
つばめ接骨院→https://www.instagram.com/tsubame0520/
すずらん接骨院→https://www.instagram.com/suzuransekkotu0321/
ライン
つばめ接骨院→https://page.line.me/ylz0052s
すずらん接骨院→https://page.line.me/beq9734a
こんにちは!
つばめ接骨院です!
正式名称が急性疼痛性頚部拘縮って知ってますか??
一般的にいうと「寝違え」です!!
今回は首の寝違えについてお話していきます!
首の寝違えは、日常生活の中で多くの人が経験する症状の一つです。朝起きたときに、首を動かすと激しい痛みが走ったり、首を回すことができなくなったりすることがあります。このような症状は非常に不快で、動作にも支障をきたすことが多いです。では、寝違えはなぜ起こるのでしょうか?
寝違えの原因
寝違えは、主に寝ている間に無理な姿勢を長時間続けたり、急な動作をしたりすることで起こります。例えば、枕が高すぎたり低すぎたりする場合や、横向きで長時間寝てしまった場合に首に負担がかかり、筋肉がこわばったり、関節に歪みが生じたりします。これが原因で、朝起きたときに首の痛みや可動域の制限を感じることになります。
また、過度のストレスや長時間の同じ姿勢を維持することも、寝違えを引き起こす要因となります。特にデスクワークが多い人やスマホを長時間使用する人は、姿勢が悪くなることがあり、それが首の筋肉に負担をかけてしまうのです。
寝違えの症状
寝違えの主な症状は、首の痛みと動かしにくさです。具体的には、以下のような症状が現れます。
- 首を動かすと鋭い痛みが走る
- 首を一定の方向にしか動かせない
- 肩や背中にも痛みが広がることがある
- 首の周りが硬く感じる
これらの症状は通常、数日以内に改善しますが、痛みが強い場合や長引く場合は、適切な治療を受けることが重要です。
つばめ接骨院の治療法
首の寝違えを放置しておくと、痛みが長引き、動作に支障をきたすことがあります。そのため、早期に治療を受けることが大切です。つばめ接骨院では、寝違えに対して以下のような治療を行い、早期回復をサポートします。
-
手技療法 つばめ接骨院では、手技療法を用いて、首や肩の筋肉の緊張をほぐします。専門的な技術で筋肉を解し、血行を促進することで、痛みの軽減を図ります。また、筋肉の緊張を緩和させることで、首の可動域を広げることができます。
-
温熱療法 寝違えの場合、温熱療法を行い筋肉の柔軟性を高め、回復を促進します。これにより、痛みの軽減とともに、筋肉のこわばりが解消されます。
-
姿勢指導と予防法 つばめ接骨院では、寝違えを繰り返さないように、姿勢の改善指導を行います。長時間同じ姿勢を取ることが首に負担をかけるため、定期的な休憩やストレッチを取り入れることが推奨されます。また、枕の高さや寝具の見直しもアドバイスし、快適な睡眠環境作りをサポートします。
-
運動療法 症状が改善した後は、首や肩の筋肉を強化するための運動療法が効果的です。適切なエクササイズを取り入れることで、再発の予防に繋がります。
寝違えを予防するために
寝違えは、一度起こると非常に不快で、生活に支障をきたします。予防には以下のポイントが重要です。
-
良い睡眠姿勢を保つ
睡眠中に首に負担をかけないよう、枕の高さを調整し、仰向けで寝ることが理想的です。横向きで寝る場合も、首に負担がかからないように枕の高さを適切に調整しましょう。 -
長時間同じ姿勢を取らない
長時間パソコンを使ったり、スマホを見続けたりすることは首に負担をかけます。1時間に一度は立ち上がって体を動かすことを心がけましょう。 -
ストレッチを取り入れる
首や肩の筋肉を柔軟に保つために、簡単なストレッチを日常的に行うことが予防につながります。
まとめ
首の寝違えは、普段の生活習慣や睡眠時の姿勢が原因で起こりやすいですが、早期に適切な治療を受けることで、症状は改善します。つばめ接骨院では、手技療法や温熱療法、運動療法などを駆使して、患者さん一人ひとりに合った治療を提供しています。寝違えの痛みに悩んでいる方は、早めにつばめ接骨院にご相談ください!!
ホームページ
(つばめ接骨院・すずらん接骨院)https://smr-group.jp/
インスタグラム
つばめ接骨院→https://www.instagram.com/tsubame0520/
すずらん接骨院→https://www.instagram.com/suzuransekkotu0321/
ライン
つばめ接骨院→https://page.line.me/ylz0052s
すずらん接骨院→https://page.line.me/beq9734a